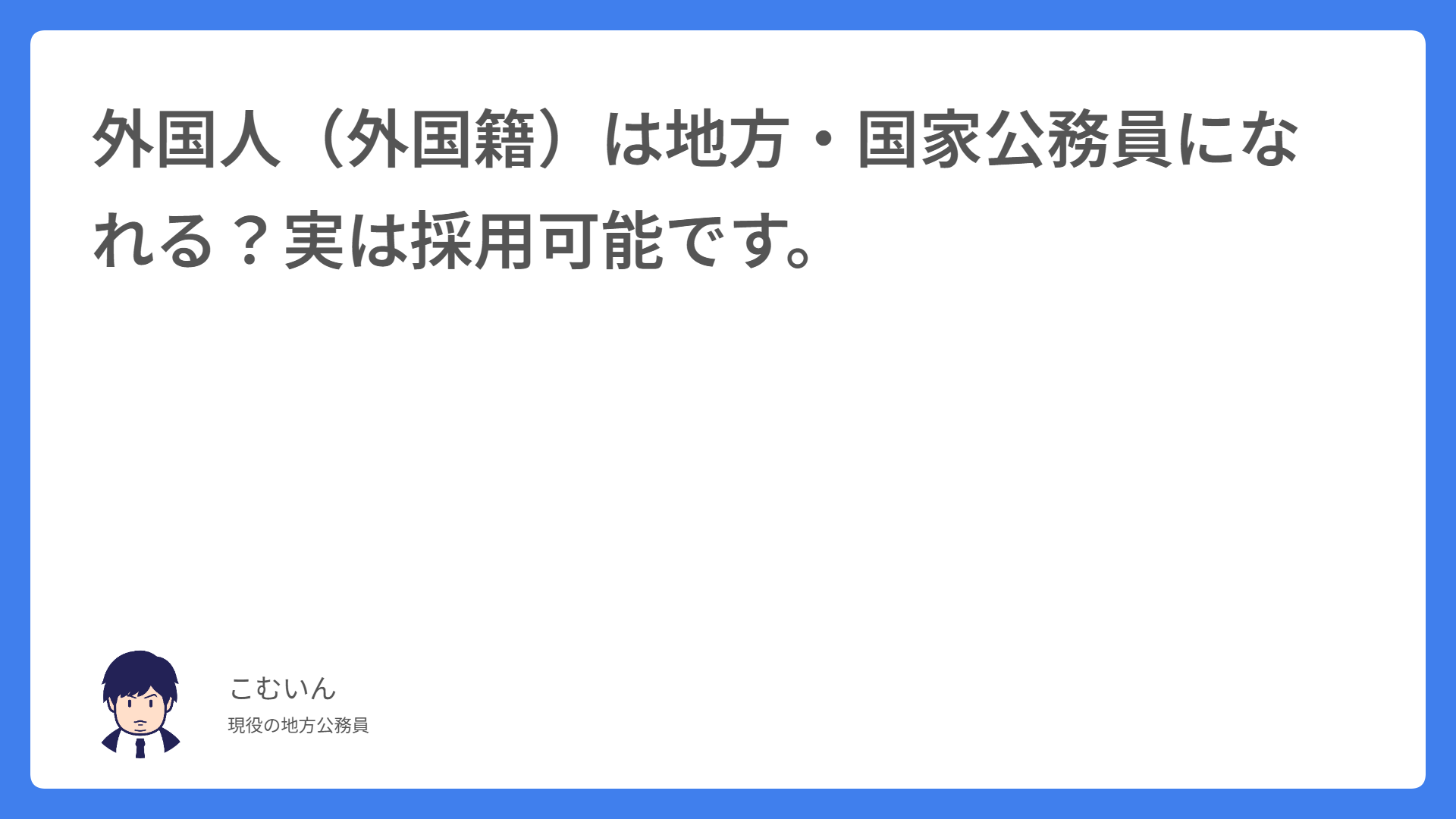なぜ?公務員試験に年齢制限はおかしい?撤廃しない理由を解説

公務員試験には「学歴」の制限が設けられています。
- 高卒者が専門卒枠や大卒枠での受験といった、いわゆる”学歴詐称”は禁止されている
- 大卒者が高卒枠や専門卒枠での受験といった、いわゆる”逆学歴詐称”は禁止されている
逆学歴詐称自体は以前は問題ではありませんでしたが、雇用機会を制限するために今は禁止されています。
同様に、公務員試験には「年齢制限」が設けられています。国や多くの地方自治体では募集要項に高卒枠、専門卒枠、大卒枠、社会人枠など募集枠によって年齢の上限が決まっています。
公務員の年齢制限は差別だ!との意見もありますが、もし年齢制限がなければ受験者は全員同じ土俵で戦わなければなりません。受験する側に立てば、年齢制限があったほうが望ましく、役所が雇用を生み出す役割を担っているという点では、競争の範囲を分ける公務員試験は妥当です。
国や地方自治体が採用時に年齢制限を設けることは最高裁判所が妥当だと認めていますが、社会情勢を踏まえ、自治体によっては年齢制限を引き上げたり撤廃したり対応は様々です。
なぜ、公務員に試験に年齢制限があるのか、現役の地方公務員が解説します。
公務員試験の年齢制限は日本国憲法違反ではない
公務員試験の採用条件に年齢制限を設けることは、日本国憲法に規定されている「職業の選択の自由」を制限しているのではないか?という議論がよくなされます。しかし、公務員試験はいつでも誰でも平等に受験することができる試験のため、公務員試験の年齢制限は職業選択の自由を制限していません。
例えば、高校を卒業した18歳、大学を卒業した22歳、民間企業で働いていた28歳、すべての段階で公務員試験を受験する権利はあります。誰しも20代を経験して30代になるわけで、いつでも年齢制限以下の年齢で受験することができたわけです。
公務員試験に年齢制限があることはおかしい!撤廃すべき!という意見は理解できますが、あえて強い言葉で返すとすれば、いつでも受けられた試験を受けなかったのはあなた自身の選択です。
民間企業も実質的には年齢制限をしている
公務員試験の年齢制限撤廃への理由の一つに、民間企業の採用には年齢制限がないという意見があります。大卒卒や大学院卒といった学歴の条件をクリアすれば、年齢制限に関係なくエントリーできるのが民間企業の採用です。
しかし、建前上の話であって、現実はそう単純ではありません。定年まで残り1年の何の実績もない59歳の人を採用する企業はありません。採用コストのほうが圧倒的に高くメリットが1つもないからです。
「年齢制限」を表に出している公務員試験か、裏で隠している民間企業の採用試験かの違いです。
雇用対策法では年齢制限禁止を義務化(年齢制限を撤廃)
厚生労働省は2007年10月に雇用対策法を改正し、年齢制限禁止を義務化しています。
雇用対策法第10条「一般的な雇用において年齢制限を設けてはいけない」。法的には年齢制限は撤廃されています。
2007年以前は雇用に関する年齢制限は「努力義務」として定められていました。企業側は、同じ能力であるなら年齢が若い人を雇いたいのが心情です。そのため、企業の中には年齢だけを見て不採用という事例が多く見受けられたのです。
しかし、バブル経済の崩壊、リーマンショック、社会情勢が雇用に大きな影響を与えます。年齢制限があれば不景気時に職に就けなかった人は一生就職できない事態になります。ニートやアルバイトが増える一方では日本経済は回復しません。
雇用対策法は公務員の採用試験の年齢制限を禁止していない
雇用対策法では公務員は対象外としています。
- 雇用対策法第10条 一般的な雇用において年齢制限を設けてはいけない
- 雇用対策法第38条第2項 同法第10条は国家公務員及び地方公務員については適用しない
公務員試験の年齢制限について国会で審議されたことがある
国家公務員法27条・地方公務員法第13条において、「国民はこの法律の適用について平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は例外のほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない」と規定してます。
公務員の年齢制限に関して以前に国会で審議されたことがあるようですが状況は変わらずでした。
公務員試験の年齢制限については最高裁判所の判決がある
公務員試験において、試験募集時に年齢制限をしても問題がない理由は、最高裁判所が「公務員試験において年齢制限を設けることは違法ではない」と判断を下しているからです。
(1)わが国の雇用慣行を前提とすると、一定年齢以下の若年層に優先して就業機会を与えることは、社会的に是認されていて、不合理であるということはできない
(2)わが国の雇用形態に変化の兆しがあるものの若年層への優先的な就業機会が妥当性を欠くに至っていない、2001年の雇用対策法も例外指針で長期勤続キャリア形成を図る場合を認めている
人事院による年齢制限を撤廃する方向での意見表明は本件合理性の判断を左右しないとして、年齢制限を設けることは、行政側の裁量権の範囲内という判断が示された(東京地方裁判所平成16年6月18日判決、最高裁判所平成17年4月19日判決)
この最高裁判決により、公務員の年齢制限を廃止することを民意で争うことは難しくなりました。
年齢制限が撤廃された事例
文部科学省などの「非常勤」の職員募集に年齢制限がされていました。しかし、合理的な理由がないとして「年齢制限の撤廃」や「募集期間の延長」が行われました。非常勤職員に限っての話で、正規職員の年齢制限が撤廃されたわけではありません。
また、明石市など正規職員の年齢制限を撤廃した市役所もあります。民間企業からの転職者の年齢制限を35歳から40歳へ引き上げるなどしている地方自治体もあります。
なぜ、公務員試験に年齢制限があるのか
公務員試験に年齢制限を設けることは、雇用対策法の対象外と規定されていること、最高裁判決で妥当性が認められていることなどが理由です。
役所は雇用創出という社会的な役割があります。公務員試験において年齢を制限しなければ完全なる自由競争になります。高校や大学を卒業したばかりの学生と民間企業に何年も勤める人が同じステージで戦うことになります。若者の就職の難易度は上がり終業機会は減ることは社会全体にとってよくありません。
また、公務員組織は、癒着を防ぐため定期的に人事異動があります。異動にたびに業務を引き継ぎながら仕事をしていく必要があり、扱う法令も多岐にわたります。このような環境下では、単純に勤続年数がものをいいます。長い勤続年数を前提に組織されているため、年齢制限を設けるほうが効率的なわけです。
公務員試験において、高齢ほど合格できないことは不公平だという意見も聞きます。これは極論ですが、能力が同じであれば、当然、若い人を採用するはずです。
- 公務員に関連する業務経験はない40歳と22歳
- 定年退職まで残り1年となった59歳と40歳
- 大学卒22歳と職歴ゼロの29歳
これは極論ですが、能力が同じであれば、当然、若い人を採用するはずです。当然、年齢の増加とともに能力を求められることになります。求められる能力に満たない場合は、真っ白な新人を育てて組織に染めていったほうが効率的と判断され不採用となっているわけです。そこに公務員試験と民間企業の採用試験の違いはありません。
ある程度の年齢であれば、それに見合う技能や知識がなければ転職は困難です。わざわざ高年齢の無能をとる企業はありません。利益を追求する、その点では公務員よりも民間企業のほうが厳しいはずです。
年齢制限という点では、市長や衆議院議員は満25歳以上、知事や参議院議員は満30歳以上、と立候補できる年齢条件があります。
少し本筋ではありませんが、将棋のプロ棋士になるためには、奨励会に入会し満26歳までに四段になる必要があります。社会人からプロになる方法もありますが、多くの人が26歳で別の人生を選ぶことになります。年齢制限はプロ棋士になることを強制的に諦めさせ別の人生の道を歩かせるために設けられています。このように年齢制限を設けること自体は必ずしも悪いということではありません。