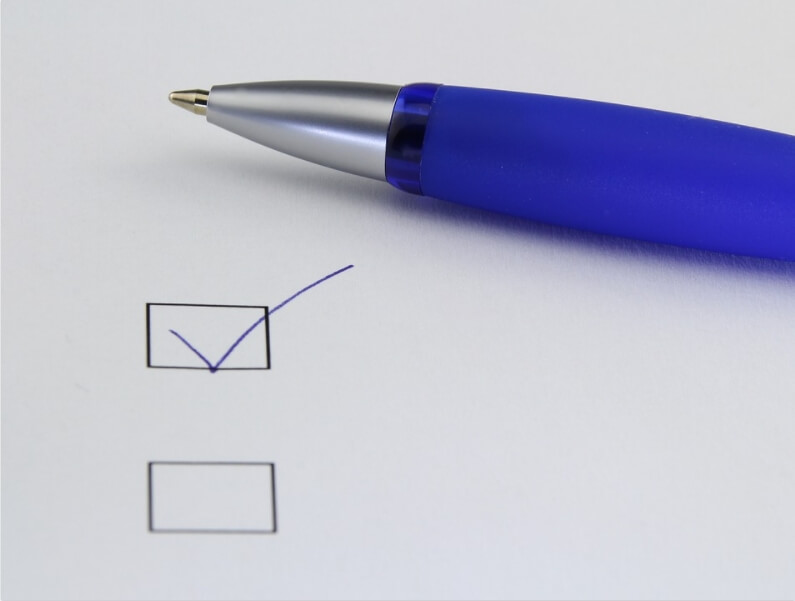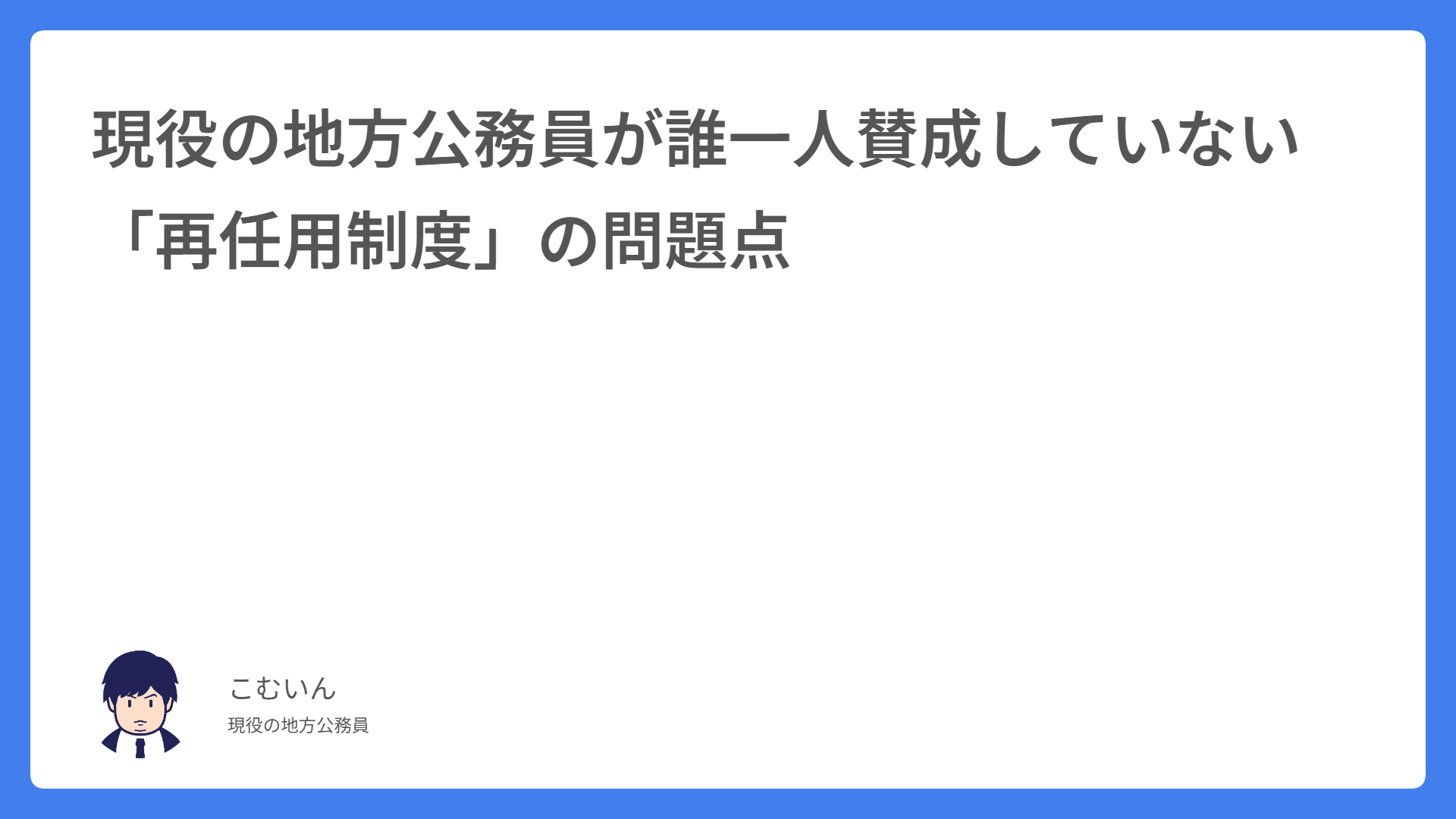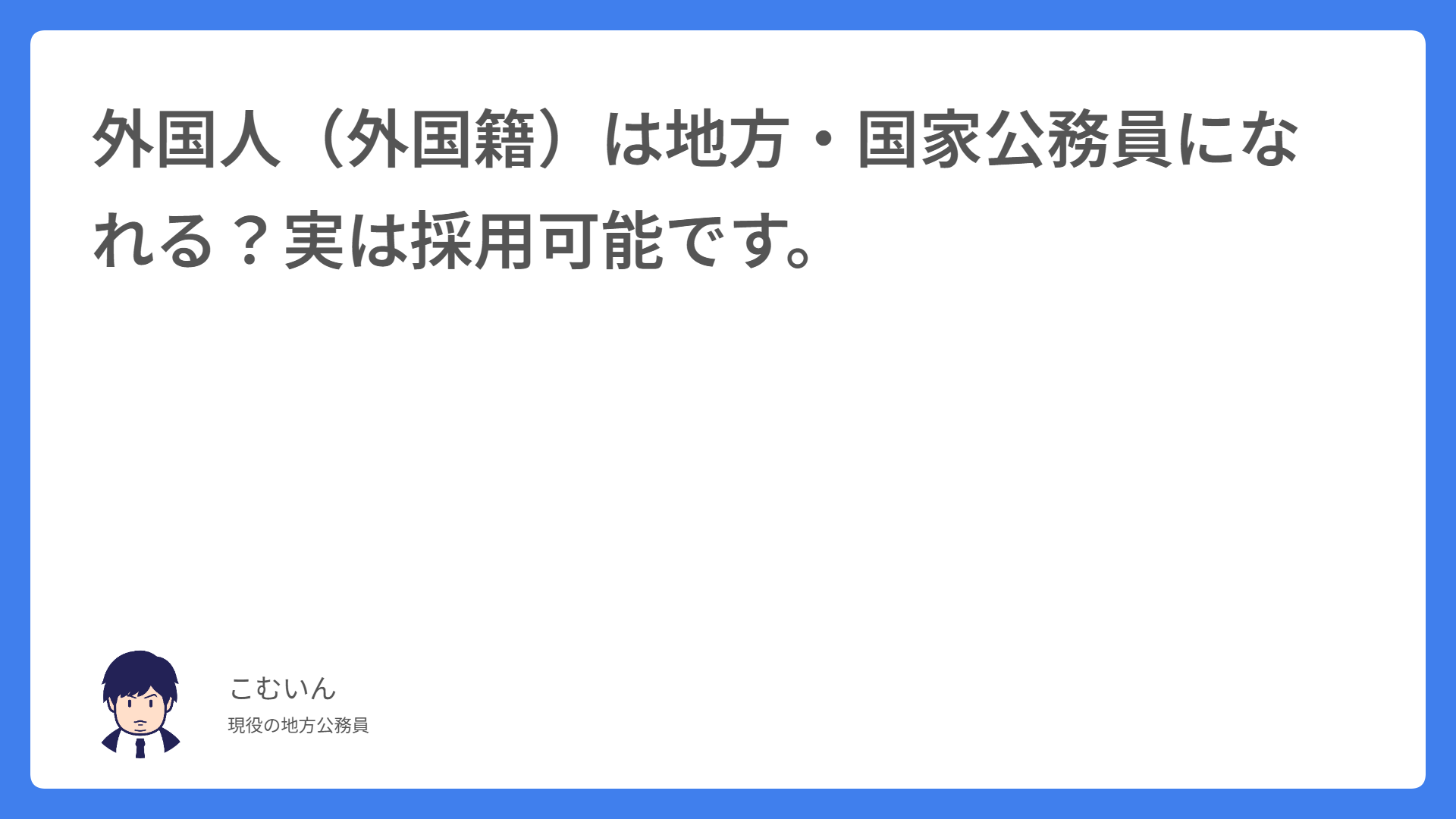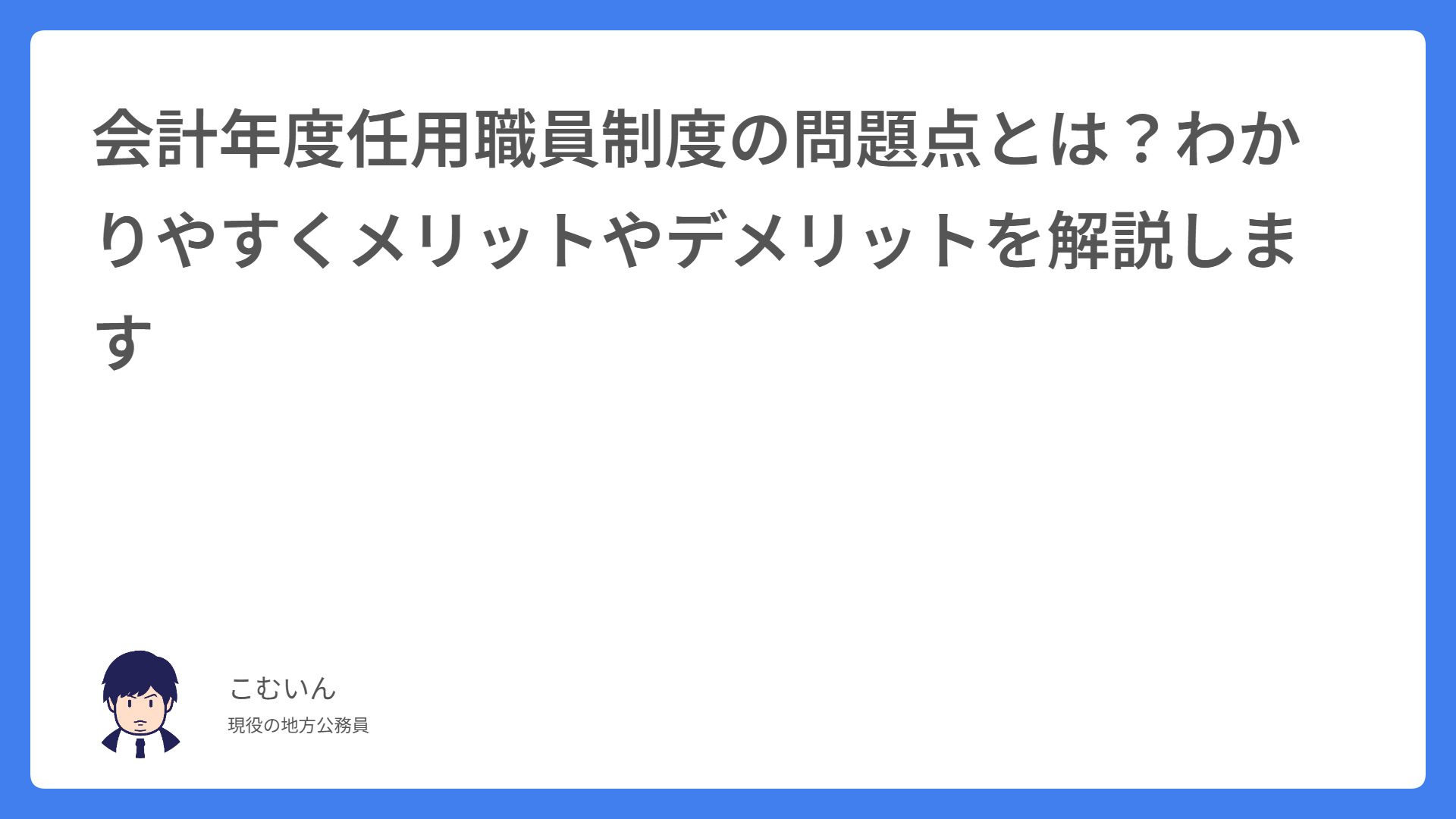ゴミ収集作業員(地方公務員)になる方法を解説、個人的にはおすすめしません

ゴミ収集作業員になる方法は2パターンです。
- 地方自治体の正規職員として採用される
- 民間企業に就職して自治体から委託を受ける
地方公務員として働くゴミ収集作業員になるためには、ゴミ収集作業員として自治体に採用されるためには、公務員試験に合格する必要があります。学歴不問のため難しい試験でありませんが、採用試験自体を実施していない自治体がほとんどなのがネックです。
一度採用されれば、問題を起こさない限りはクビにはならないのが公務員。ゴミ収集作業員になりたいという人も多いでしょう。ゴミを集めるだけなんて楽勝!仕事も早く終わって給料が高いなんて最高!だと思っているなら、考え直してください。現実は甘くありません。
年収は行政職と大差なく、民間企業とは最大で3倍ほど違います。お金だけでみればコストパフォーマンスは最強かもしれませんが、私はオススメできません。
ゴミ収集作業員にな方法、給料や仕事内容について現役の地方公務員が解説します。
ゴミ収集作業員は地方公務員
ゴミ収集作業員の定義は「単純な労務に雇用される一般職の地方公務員」です。
公務員は採用区分が細分化されており、ゴミ収集作業員は「現業職」に該当します。役所の窓口は行政職です。呼び方は地方自治体によって様々で、現業職=労務職=技能職=作業職、など表現が異なります。
ゴミ収集作業員は、土木作業員、バス運転手、学校給食員、学校用務員、清掃員、守衛、運転手、と同じカテゴリーになります。
仕事内容
ゴミ収集作業員とは、家庭や企業から出た可燃ゴミ、缶・ビン・ペットボトル、発泡スチロール、不燃ごみなどを収集する作業をする人です。
基本的に2人1組で毎日決められたコースをまわり、ゴミを回収すれば作業車を清掃しその日の業務は終了になります。
業務時間は(始業終業やお昼休み)各自治体に準じますが、朝は早いことが多いです。15時には作業を終え、作業場でお風呂に入り、終業まで待機が一般的な1日のスケジュールです。
毎日決められたコースをまわるため、ゴミ収集が早く終われば早く仕事を終えることができます。ゴミ収集車の運転や作業が荒いのはそのためです。
休暇や給料(ボーナス)は地方自治体と同じ基準
現業職は地方自治体の正規職員です。地方自治体が定める制度と同じものになりますから、実は福利厚生や年収などの各種データは各自治体のHPに公表されています。
有給休暇日数や休職制度なども行政職と同じですが、給料だけは行政職と異なり現業職の給与表になります。ボーナスの支給月数は行政職と同じです。
平均年収は行政職>労務職になります。現業職には部課長級(管理職)はありませんので、役職のない行政職と比べればそれほど大きな差はありません。行政職には認められない手当も現業職には支給されます。
具体的な年収については、総務省が毎年「地方公務員給与実態調査」で公表しています。
- 平均月収:約41万円(平均年収:約650万円)
- 平均年齢:約50歳
多くの自治体では現業職の新規採用を凍結しています。また、給料カットできませんからベテラン職員の給与は高いまま維持されています。そのため、民間企業と比べて、約1.5倍~2倍の年収になります。
ゴミ収集作業員になるには公務員試験に合格する必要がある
ゴミ収集作業員は地方公務員ですから、公務員試験を合格することが必須条件となります。行政職の採用試験とは全く異なり、試験自体は非常に簡単です。極端にいえば、足し算と引き算ができれば合格というレベルです。
しかし、社会的背景によってゴミ収集作業の民間委託が進み、採用自体が少ないため採用倍率は高くなっているのが実情です。
採用試験自体を実施していない自治体が多い
現代の地方自治体のトレンドは、現業職の廃止です。現業職を正規職員として雇用するコストは、民間委託するコストの2倍~3倍になります。
民間企業へ委託したほうがはるかに安く、直営をもつ意味が薄れてきており、既にバスの運転手や学校給食員などの多くは民間へ委託されています。そのため、現業職の採用を実施していない自治体がほとんどです。仮に募集があっても数名程度ですから、倍率は高くなる傾向にあります。
京都市では、2012/13年度から一時的に採用を凍結していた新規採用試験を2022年に再開し5人程度の採用試験を実施しています。9年ぶりですからチャンスを逃さないように情報をキャッチする必要があります。
運転免許が必要
普通免許は絶対に必要です。
一般的な重量のパッカー車であれば2トンなので普通免許でも運転できますが、業務内容によって普通免許以上が必要となる場合があります。
ゴミ収集車の運転には中型(8トン限定を含む)以上の免許があればすべての業務に対応できるはずです。自治体によって求められるレベルは異なりますので、応募要件を確認してください。
学歴は基本的に不問
行政職であれば、高卒や大卒といった枠で受験する必要がありますが、ゴミ収集作業員になるための学歴は基本的に問われません。
しかし、高卒以上、逆に大卒以上は不可といった一定の資格制限を設ける自治体もありますで、募集要項を要チェックしてください。
年齢制限あり
公務員試験ですので、年齢制限があります。一般的には35歳から40歳までが申し込める上限となっています。

ゴミ収集作業員になることをオススメできない理由
言葉を選ばずにあえて厳しく言えば、ゴミ収集作業員には誰でもなれます。公務員試験はあってないようなものだからです。
毎日、決められたルートを回ってゴミを回収する、実働時間は1日5時間程度、福利厚生や年収も行政職と変わらないのであれば目指す人がでてくるのもうなづけます。しかし、オススメはできません。
ゴミ収集作業は想像以上にきつい
なかには、お風呂なんて家に帰ってから入れ!税金の無駄だ!と怒る人もいるかもしれません。しかし、ゴミ収集作業員は世間が思っているほど楽な仕事ではありません。
完全な肉体労働なうえ、衛生面には細心の注意を払わなければいけません。パッカー車とすれ違うだけで異臭で呼吸ができないといった経験が一度はあると思いますが、それを毎日浴び続けるわけです。髪の毛や作業服にも匂いは付着しますから、洗い流さなければそれこそ外も歩けません。夏場のゴミ収集なんて地獄ですよ。
ゴミ収集作業員という仕事は、典型的な3Kです。3K(きつい、汚い、危険)とは主に土木業界で使われる用語ですが、昔から3Kの仕事は高給です。なぜなら、誰もやりたくないからです。
体育会系の頂点
ゴミ収集作業員は民間委託が主流になるまでは毎年計画的に採用されています。自治体の役割は雇用を生み出すことでもあります。昔は自治体直轄が常識で逆に民間委託が異端であったわけです。そのため、40代から上の世代の多くが未だ現役です。
一方、20代、30代は採用が凍結されていれば0人です。仮に自治体が直営に舵を切って採用を開始したとしてもかなりいびつな年齢構成になります。
端的にいえば、かなりこき使われると思ってください。今採用される人は一番下っ端です。例えば京都市の事例ですと、職員数は2006年度の999人から、2021年度は半分以下の417人になっています。職員の割合はいびつです。
- 50~60歳 208人
- 40代 190人
- 30代 18人
- 20代 1人
これは新規採用を凍結しているためですが、民間企業への委託割合も、2006年度の26%、2021年度は63%となっており、今後も民間委託の方針は変えないとのことです。
私が知っている現業職の世界は、後輩に人権は存在しない、パワハラなんて当たり前の世界です。40年制の中学校をイメージをすれば分かりやすいかもしれません。何度か仕事を一緒にする機会があったのですが、民間委託の流れも納得せざるを得ない状況でした。
学歴不問、試験はあってないようなもの、裏を返せばそういった人間の雇用を生み出す自治体の役割である側面を考えてみてください。
定年退職まで続けられるか不透明
郵政民営化によって公務員だった人が分限免職となり公務員でなくなるケースがあるように、風向きが変わるかもしれません。
バスや鉄道の民営化によって、運転手が事務仕事をしているケースは多くあります。運転手として30年間勤務していて、来年から生活保護担当(ケースワーカー)をする可能性があるのが公務員です。
民間委託する流れが変わらない以上、定年退職までずっとゴミ収集作業員として勤務できない可能性のほうが高いと思います。
一方で100%民間委託することはデメリットもあります。災害時などの緊急事態に民間では稼働できない可能性があるからです。そのため、非常時に対応できる直営体制は一定数維持するものと思います。
今や狭き門となったゴミ収集作業員になりたい人は自治体のHPや採用情報を定期的にチェックしてください。数年に1度の採用もザラですからチャンスを逃すと年齢制限に引っかかってしまい公務員試験の受験資格を失ってしまっては元も子もありません。