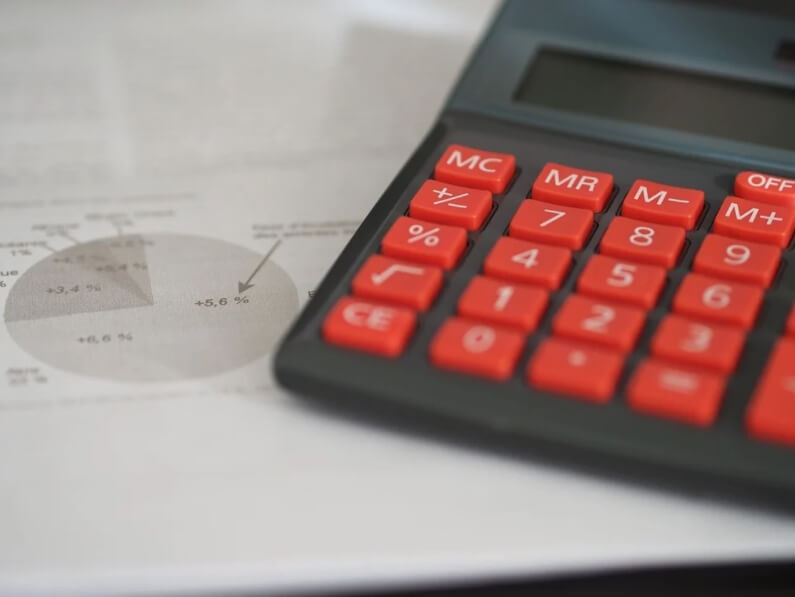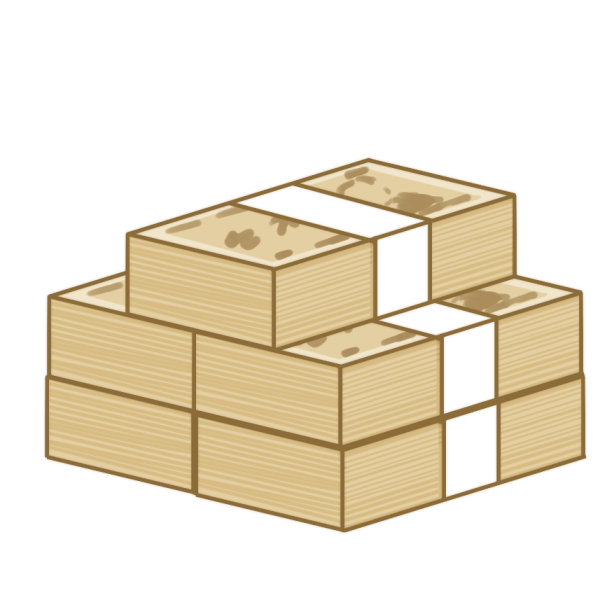なぜ…公務員にボーナスの支給はおかしい!?廃止すべき?

公務員にボーナスを支給すること自体おかしい、間違っているという声を多く聞きます。
- なぜ、利益をあげていない公務員にボーナスを支給するのか?
- なぜ、民間企業の平均額を支給するのか?
- そもそも、税金だぞ!
公務員にボーナスをあげるくらいなら、
税金を納めている私たちの負担を少しでも軽くしてくれ、今すぐ廃止しろ!という気持ちは分かります。
しかし、私はおかしいとは思いません。
なぜなら、公務員の給料の原資は確かに税金ですが、労働に対して支払われる対価だからです。
※公務員の場合は、「期末手当」と「勤勉手当」の合計が、民間企業に勤めるサラリーマンのボーナスと同じ意味になります。
本記事では、便宜上「ボーナス」とします。
公務員は利益を出さないので、ボーナスは不要?
ボーナスは賞与ですから、会社の経営状況によってもらえる額は異なります。
基本的には、会社の利益が上がれば多くもらえ、下がれば少なくなります。
しかし、ほとんどの地方公共団体は毎年、赤字です(資金が潤沢なのは東京都ぐらい)。
にもかかわらず、公務員は、いつの時代も安定してボーナスが支給されています。
バブル期はもちろんのこと、リーマンショックの時も。
公務員だけおかしい!景気と給料は比例すべきだ!と思う気持ちは分かります。
しかし、赤字であればボーナスを出さない企業が多いかというと、実態はそうではありません。
そもそも、ボーナスの意味(定義)は各会社によって異なります。
- ボーナスは賞与であり、利益に基づいて支払うもの(以下、①)
- 年間の所得の一部を定時期に払うもの(以下、②)
昔は①、現代は②の考え方が主流となっています。
例えば、厚生年金保険料。
厚生年金保険料は、10年ほど前までボーナスに対して1%負担でしたが、現在は月給与と同割合徴収されます。
また、住宅ローンやマイカーローン。
住宅ローンも銀行はボーナス返済を認めています。
でるかどうかもわからないボーナスを含めて融資することは銀行にとってリスクでしかありません。
にもかかわらず、ボーナスを前提にローンを組むことを推奨しているのです。
これらの事実からして、民間企業は給与の一部をボーナスで支払っていることが伺えます。
年間の所得の一部を定時期に払っている裏付けでもあります。
つまり、現代において日本の会社の場合は②がほとんどなのに、公務員にだけ①を求めるような意見は筋が通りません。
公務員のボーナス支給をどちらで定義するかにもよりますが、
①で考えればおかしいですし、②で考えればおかしくありません。
私は、この考え方の違いが議論を混乱させてしまっている原因だと考えています。
現時点で公務員のボーナスを廃止するという議論をしても、
月の給料にその分を上乗せするということで対応されることになるでしょう。
形が変わるだけです。
仮に、日本のほとんどの企業が成果を出した従業員にのみボーナスを支給するという社会になれば、その流れは公務員にもくると思います。
そもそも公務員という仕事は利益を出してはいけない
公務員もボーナスの支給額を業績で評価すればいい
そんな意見もあるでしょう。
※国や一部の地方自治体では、既に評価制は導入されており、業務成績によってボーナスや昇給額は違います
公務員の業績はどう評価するのでしょうか。
- 生活保護費を支給しないことが成果でしょうか
- 公共工事をしないことが成果でしょうか
どちらも税金を使っていませんよ・・・違いますよね?
生活保護が必要な人には適切に支給しなければ人命にかかわりますし、
歩行者を車から守るような必要な公共工事もあるはずです。
そのため、公務員の仕事は表に出る数字では評価できません。
また、自治体が赤字だからといって、
- 道路を歩く際には1,000円徴収します
- 生活保護の支給を廃止します
- 保険料は5割負担です
- 水道料金を10倍にします
- 路線バスは全線廃止します
このようなことを強行すれば、一年で黒字にできます。
しかし、これが許されるでしょうか。
あり得ないですよね?
では、なぜあり得ないのでしょうか。
あなたが税金を納めている納税者だからでしょうか。
道路を歩けるということは、役所の土地を歩いていることになります。
水道が使えるということは、役所が整備した設備を使っているということになります。
それって、当たり前のことでしょうか。
無意識に「役所だからやってあたりまえ」という思考が働いていませんか。
- 携帯会社に携帯料金を払わずに携帯電話を使用できますか?
- 不動産会社(貸主)に家賃を払わずに家を借りられますか?
当然、対価としてお金を払いますよね。
税金を納めていないのであれば、
道路を歩く際に1,000円徴収、水道料金は10倍にします。
こう言われて腹が立つのであればやめればいいんです。
道路も歩かず、水道も使わず、バスも使わず。
(引っ越せばいい?隣の自治体も同じことになっていますよ。)
これができるのが民間企業です。
これをしているのが民間企業です。
これが言えるのが民間企業です。
路線バスなんてどこも赤字です。
でも、廃止すれば住民の生活が成り立ちません。
民間企業であれば、撤退、倒産しても仕方がないですみますが、
役所は赤字でも続けなくてはいけません。
役所の利益ではなく国民(住民)の利益を優先するために公務員が必要なのです。
この前提が公務員と民間企業の決定的な違いです。
公務員の仕事は平等ではなくてはいけません。
あっちをたてればこっちがたたない。
その調整をするのが公務員です。
公務員に成果主義を導入すれば、成果がでない仕事は誰もやらなくなってしまいます。
利益を上げればいいとなれば、犯罪を取り締まるかどうかも、被害者がお金を出せるかどうかで決まるんですよ?
役所に文句を言いにいっても、納税額が低いと話も聞いてくれないし、役所にすら入れてもらえないかもしれません。
怖くないですか?そんな世界・・・
もちろん、あえて極端な例としてとりあげてたまでで、このようなことはありえません。
しかし、公務員が利益を追求すればこうなる未来もあり得るということです。
公務員のボーナス支給額は多いの?少ないの?
公務員のボーナスが多いか少ないか、どうやって決まるのか、なぜ民間企業の平均なのか。
詳細は、「【2019最新】公務員の夏・冬ボーナス平均支給額は?支給日はいつ?」をご覧ください。
公務員の給料とボーナスは、バブル期と今でほとんど変わらない
公務員は、好景気、不景気に関係なく安定して給料が支給されます。
バブル期では、民間企業に勤めるサラリーマンからすれば、公務員になる人はよっぽどでした。
愛国心があるか、バカか。
そんな言われ様でした。
それも当たり前です。
何もしていない学生が就職活動を始めれば、面接もせぬまま何社からも内定がでます。
内定辞退させないために(ほかの会社へいかせないために)海外旅行に無料で長期間つれていってくれます。
交通費も1日1万円もらえたり、ボーナスは札束が立つ(ほど多額)んですよ。
一方、公務員は、バブル期と今を比べても、給料とボーナス額はほとんど変わっていません。
昔から試験もありますので勉強必須です。
もし私がバブルに生きていれば、絶対に公務員という仕事は選択しないでしょう。
役所の大先輩に話を聞くと、民間と公務員では、初任給ですら倍以上違ったようです。
好景気の時は哀れみの目で卑下され、バブルが崩壊しリーマンショックなど不景気になれば叩かれます。
- 民間が給料を多くもらっていた時は、公務員はそのまま底辺にいろ
- 民間の給料が下がれば、公務員はもらいすぎだから底辺に合わせろ
それが公務員の立場であり、相手にする仕事なんです。